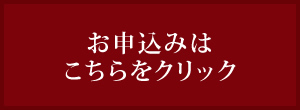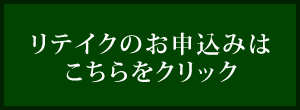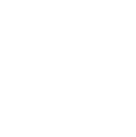身体の基礎知識ベーシックコース(11日間)オンライン開催
こちらの講座は終了いたしました
2023年4月開講
今期は自宅から受講できてアーカイブも活用できる
オンライン受講にて開催します。
解剖・運動学テキストまるまる一冊分をコンプリート!
現場で使える解剖・運動学の知識を、医療現場のスペシャリスト3名がわかりやすくお伝えします。
日々の現場での指導において、より深い知見から自信を持ってアプローチをしたい方、是非ご参加ください。
本年度は前回の開催においてもニーズの高かった「オンライン開催」で開講いたします。
講義は毎回終了後に復習用としてアーカイブ配信をいたしますので、リアルタイムで参加できなかった日も動画で補講が可能です。
解剖・運動学の知識がなくてはアプローチができない
一線で活躍するトレーナーの中には、ひとりひとり違うクライアントのケガや痛みといった障害をきちんと評価し、適切なアプローチを提供するためには「解剖学や運動学の知識がなくては仕事ができない」と言い切る方も少なくありません。
しかし解剖・運動学を学ぼうとしても、これまでは特定の部位のみを取り上げたセミナーや講座に留まり、全身的な連動性までも理解する機会は、ほとんどありませんでした。
本当に現場で必要とされるのは、解剖・運動学の総合的な知識
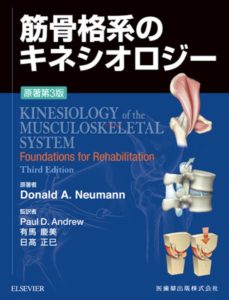 そこで今期の「身体の基礎知識ベーシックコース」では、オンラインにて5ヶ月間で11回の講義(1日あたり基本は90分×2コマ)を行い、解剖・運動学を体系的に学べるカリキュラムをご提供いたします。
そこで今期の「身体の基礎知識ベーシックコース」では、オンラインにて5ヶ月間で11回の講義(1日あたり基本は90分×2コマ)を行い、解剖・運動学を体系的に学べるカリキュラムをご提供いたします。
日々、現場で活躍する医療国家資格者3名を講師に迎え、講義テキストに『筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版』(医歯薬出版社 定価¥13,750)を用います。
率直に申し上げて、このボリュームのテキストを一人で読み切ることは難しいと思います。
そこで本コースでは、講師が導き役となりテキストの内容をわかりやすくお伝えします。また、その知識が現場に繋がるよう、講師の現場での経験を交えて講義を行います。
そのため、初学者の方はもちろん、熟練者の方にも楽しんで学んでいただけるコースです。
医療と運動の架け橋になる講座
3名の講師の先生方は、上記のように今回の講座を位置づけています。
なぜなら、今後医療保険制度の改正により医療現場ではリハビリを保険適用内で提供できる期間が減少して行くからです。
そこで「医療現場と運動現場が対等にコミュニケーションを図り、プログラムを組める知識を身につけていただく」ことが講師たちが本講座で目指しているゴールです。
講座概要
テキストとして『筋骨格系のキネシオロジー』(医歯薬出版社 定価¥13,750)を用い、本教材をベースとした全20コマ(1コマ90分)の講義とそれを確認するための修了テスト、さらに実際のクライアントの動画を見ながら学習した知識を応用するためのディスカッションを行なうカリキュラムで、身体に携わる仕事に必要な医学の基礎である解剖学・運動学・生理学を学びます。
1日あたり講義は2コマもしくは3コマ。計11日間開講いたします。最後には確認テストを行い、合格点に達した方に修了証を発行いたします。
| 対象 | パーソナルトレーナー・ボディーワーカー・理学療法士・セラピスト等の身体に携わるお仕事されている方、またはそれらを目指している方 |
|---|---|
| 受講料 | ¥154,000(税込) ※コース料金には、復習用アーカイブ映像も含まれます。 ※お支払い方法は銀行振込となります。 ※分割2回払いの設定もございます(申し込み後10日以内に半額振込、残りを2023年4月3日までに振込) ※別途コースの教科書として『筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版』(医歯薬出版社 定価¥13,750)を使用いたします。お持ちでない方は、初回までに各自ご購入のうえご持参ください。 |
| 受講方法 | ZOOM(オンライン)受講 申し込み後ミーティングルームのURLをお送りいたします。毎回アーカイブ配信をいたしますので、リアルタイムでの参加が難しい日は動画で補講していただけます。 |
| 日時 | 2023年 (1)4/9, (2)4/23, (3)5/7 (4)5/21, (5)6/4, (6)6/18, (7)7/9, (8)7/23, (9)8/6, (10)8/20, (11)9/3[全11日] (1) – – – – – – – 10:00〜14:20(開校式:40分,90分×2コマ 途中30分の休憩あり) (3)~(10) – – – – 10:00〜13:10(90分×2コマ) (11) – – – – – – 10:00〜13:20(90分×1コマ,修了テスト:45分,ディスカッション:90分,修了式:15分) |
再受講(リテイク)について
過去に開講した本コースにご参加いただき、身体の基礎知識ベーシックコース修了証をお持ちの方は、単元ごとに単発で再受講(リテイク)をしていただけます。
※筋骨格系のキネシオロジー原著第3版がリリースされたことを受け、2021年に講義内容を再編し、講義スライドも一新いたしました。
また、より深く内容をお伝えできるよう、各講師が現在の現場で頻繁に関わることのある関節をお話しするように担当単元を一部変更しております。
日々レベルアップし続けている講師陣にも是非会いに来てください!!
| 対象 | 過去に開講した本コースにご参加いただき、身体の基礎知識ベーシックコース修了証をお持ちの方 |
|---|---|
| 受講方法 | ZOOMによるオンライン受講となります。 リアルタイムでの参加が難しい方は、アーカイブ配信のみでの受講も可能です。 申し込み時に備考欄からお知らせください。 |
| 受講料 | 1コマ(90分)につき¥3,300(税込) ※筋の各論0.6コマは¥1,980(税込)、体軸骨格(骨・関節)1.4単元は¥4,620(税込)といたします。 ※申し込みはこのウェブサイトのお申し込みフォームから承り、お支払いはpaypalでのクレジット決済となります。 |
カリキュラム概要 (原則1単元90分)
| 単元名 | 単元数 | 講師 | 開講日 |
|---|---|---|---|
| 開校式 | o.4 | 岡本 | 4/9 |
| 関節総論 | 1 | 柳 | 4/9 |
| 筋総論 | 1 | 川上 | 4/9 |
| 筋各論 | 0.6 | 岡本 | 4/23 |
| 体軸骨格 (骨・関節) |
1.4 | 岡本 | 4/23 |
| 体軸骨格 (筋・換気) |
2 | 岡本 | 5/7 |
| 肩関節 肘と前腕(骨・関節) |
2 | 柳 | 5/21 |
| 肘と前腕(筋) 手関節〜手 |
2 | 柳 | 6/4 |
| 股関節 | 2 | 岡本 | 6/18 |
| 膝関節 | 2 | 岡本 | 7/9 |
| 足関節 | 2 | 川上 | 7/23 |
| 歩行 | 2 | 川上 | 8/6 |
| 走行 | 2 | 川上 | 8/20 |
| ディスカッション | 90分 | 全講師 | 9/3 |
| 合計 | 20単元+α | ||
カリキュラム詳細
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 開校式 | 岡本 | 40分 | ・本講座の概要説明~講師紹介 ・受講生自己紹介 ・「筋骨格系のキネシオロジー」について |
| 要約 | 本講座のイントロダクションとして全11日間の流れをお伝えしつつ、「筋骨格系のキネシオロジー」をテキストに選出した理由やその使い方についてご説明します。 | ||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 開校式 | ・本講座の概要説明~講師紹介 ・受講生自己紹介 ・「筋骨格系のキネシオロジー」について |
| 要約 | 本講座のイントロダクションとして全11日間の流れをお伝えしつつ、「筋骨格系のキネシオロジー」をテキストに選出した理由やその使い方についてご説明します。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 関節総論 | 柳 | 1 | ・第1章 はじめに(一部) ・第2章 人体関節の基本的構造と機能 |
| 要約 | 身体運動学に関連する入門的な用語を解説します。 ヒトの身体は200個以上の骨で構成され、身体の動きは個々の関節で骨が回転することによって起こります。 本講義では、関節の構成要素や分類、組織学、機能的な側面について解説します。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 関節総論 | ・第1章 はじめに(一部) ・第2章 人体関節の基本的構造と機能 |
| 要約 | 身体運動学に関連する入門的な用語を解説します。 ヒトの身体は200個以上の骨で構成され、身体の動きは個々の関節で骨が回転することによって起こります。 本講義では、関節の構成要素や分類、組織学、機能的な側面について解説します。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 筋の総論・各論 | 川上 岡本 |
1.6 | ・第1章 はじめに(一部) ・第3章 筋:骨格系の主要な安定器そして運動器 ・第4章 生体力学の原理 |
| 要約 | 総論(川上担当分)ヒトの運動において筋の解剖学的・運動学的な知識は重要で現場でも必要となってきます。各関節を動かすため筋はどのような構造をしており、どのように力を生み出していくのか。そもそも筋は全身同じような構造をしているのか。筋の総論では筋を運動力学的な視点から解説し、今後の各関節の単元で関節運動の理解に繋がるようにお話しさせていただきます。 各論(岡本担当分)総論で学んだ筋に起こる運動や不動・加齢による変化、またニュートンの運動法則を用いて筋が関節等に起こす力についてお話しさせていただきます。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 筋の総論・各論 | ・第1章 はじめに(一部) ・第3章 筋:骨格系の主要な安定器そして運動器 ・第4章 生体力学の原理 |
| 要約 | 総論(川上担当分)ヒトの運動において筋の解剖学的・運動学的な知識は重要で現場でも必要となってきます。各関節を動かすため筋はどのような構造をしており、どのように力を生み出していくのか。そもそも筋は全身同じような構造をしているのか。筋の総論では筋を運動力学的な視点から解説し、今後の各関節の単元で関節運動の理解に繋がるようにお話しさせていただきます。 各論(岡本担当分)総論で学んだ筋に起こる運動や不動・加齢による変化、またニュートンの運動法則を用いて筋が関節等に起こす力についてお話しさせていただきます。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 体軸骨格 (骨・関節学) |
岡本 | 1.4 | ・第9章 体軸骨格:骨・関節学 |
| 要約 | 第9章:体軸骨格は四肢と連結し、四肢の運動に対して安定性を提供する一方、それとは逆に四肢の運動から影響を受けることができる柔軟性も併せ持つ部位です。また脳・脊髄・内臓などのヒトにとって重要な臓器を保護する役割も持っており、極めて重要な身体部位だと考えます。本講義では体軸骨格である、頭蓋~脊柱~胸郭の形態的・構造的な特徴について解説し、それ故に生じる運動学的特徴についてお話しさせていただきます。 | ||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 体軸骨格 (骨・関節学) |
・第9章 体軸骨格:骨・関節学 |
| 要約 | 第9章:体軸骨格は四肢と連結し、四肢の運動に対して安定性を提供する一方、それとは逆に四肢の運動から影響を受けることができる柔軟性も併せ持つ部位です。また脳・脊髄・内臓などのヒトにとって重要な臓器を保護する役割も持っており、極めて重要な身体部位だと考えます。本講義では体軸骨格である、頭蓋~脊柱~胸郭の形態的・構造的な特徴について解説し、それ故に生じる運動学的特徴についてお話しさせていただきます。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 体軸骨格 (筋・換気) |
岡本 | 2 | ・第10章 体軸骨格:筋と関節の相互作用 ・第11章 咀嚼と換気の身体運動学 |
| 要約 | 第10章:体軸骨格の筋は四肢の筋と比べ、非常に複雑な走行をしています。本講義では、この筋の構造によってもたらされる、運動時の体軸骨格の安定性についてお話しさせて頂きます。 第11章:ヒトは呼吸せずに生きることは出来ません。本講義では、呼吸の目的である「換気」を解剖学・運動学的な視点からお話しさせていただきます。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 体軸骨格 (筋・換気) |
・第10章 体軸骨格:筋と関節の相互作用 ・第11章 咀嚼と換気の身体運動学(換気のみ) |
| 要約 | 第10章:体軸骨格の筋は四肢の筋と比べ、非常に複雑な走行をしています。本講義では、この筋の構造によってもたらされる、運動時の体軸骨格の安定性についてお話しさせて頂きます。 第11章:ヒトは呼吸せずに生きることは出来ません。本講義では、呼吸の目的である「換気」を解剖学・運動学的な視点からお話しさせていただきます。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 肩関節 肘と前腕 (骨・関節) |
柳 | 2 | ・第5章 肩複合体 ・第6章 肘と前腕(〜p.218) |
| 要約 | ヒトの肩は4つの関節と多くの筋肉で構成されています。 この構造と機能により、上肢に大きな可動性をもたらし、手を遠くまで動かすことが出来るよになりました。しかし、不安定な構造のため肩の障害は多く発生します。 本講義では、肩の機能と構造(骨・関節・筋)を学び、肩関節の正常運動について解説します。また、肘と前腕の骨・関節についても解説いたします。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 肩関節 肘と前腕 (骨・関節) |
・第5章 肩複合体 ・第6章 肘と前腕(〜p.218) |
| 要約 | ヒトの肩は4つの関節と多くの筋肉で構成されています。 この構造と機能により、上肢に大きな可動性をもたらし、手を遠くまで動かすことが出来るよになりました。しかし、不安定な構造のため肩の障害は多く発生します。 本講義では、肩の機能と構造(骨・関節・筋)を学び、肩関節の正常運動について解説します。また、肘と前腕の骨・関節についても解説いたします。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 肘と前腕 (筋) 手関節〜手 |
柳 | 2 | ・第6章 肘と前腕(p.218〜) ・第7章 手関節 ・第8章 手 |
| 要約 | ヒトの手は他の動物と比べ巧みな動きを可能にしました。 曲げる・伸ばす・握る・つまむ・はさむ・投げる… 手は他の部位より複雑な動きが可能です。 巧みな手の動きが、脳に進化をもたらしたとも言われています。 本講義では脳の進化への影響も加え、指・手首・前腕・肘の機能と構造(骨・筋・関節)を学び、指先から肩の連動について解説いたします。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 肘と前腕 (筋) 手関節~手 |
・第6章 肘と前腕(p.218〜) ・第7章 手関節 ・第8章 手 |
| 要約 | ヒトの手は他の動物と比べ巧みな動きを可能にしました。 曲げる・伸ばす・握る・つまむ・はさむ・投げる… 手は他の部位より複雑な動きが可能です。 巧みな手の動きが、脳に進化をもたらしたとも言われています。 本講義では脳の進化への影響も加え、指・手首・前腕・肘の機能と構造(骨・筋・関節)を学び、指先から肩の連動について解説いたします。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 足関節~足部 | 川上 | 2 | ・第14章 足関節と足部 |
| 要約 | 足は人体の中で最も末端にあり、ヒトが立つ・歩くなどの日常生活場面では必ず地面に接地しておく必要があります。そして、足がもつ複雑な機能を効率良く発揮することで、ヒトの動作はより円滑になります。また、足は地面からの反力を直接受けるため「アーチ」という機構を有しており、これは歩行時の衝撃吸収などの役割を担っています。本講義では足の機能と特性、ヒトの動きとの関連性についてお話しさせていただきます。 | ||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 足関節~足部 | ・第14章 足関節と足部 |
| 要約 | 足は人体の中で最も末端にあり、ヒトが立つ・歩くなどの日常生活場面では必ず地面に接地しておく必要があります。そして、足がもつ複雑な機能を効率良く発揮することで、ヒトの動作はより円滑になります。また、足は地面からの反力を直接受けるため「アーチ」という機構を有しており、これは歩行時の衝撃吸収などの役割を担っています。本講義では足の機能と特性、ヒトの動きとの関連性についてお話しさせていただきます。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 膝関節 | 岡本 | 2 | ・第13章 膝 |
| 要約 | 膝関節は体重を支持しなければならない荷重関節であるにもかかわらず、非常に不安定で適合性の悪い関節といわれています。この不安定な関節を安定させるために、靱帯や半月板が膝関節では重要な役割を担っています。 本講義では膝関節の持つ解剖学的な特徴や股関節および足関節の架け橋となるべく運動学についてもお話しさせていただきます。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 膝関節 | ・第13章 膝 |
| 要約 | 膝関節は体重を支持しなければならない荷重関節であるにもかかわらず、非常に不安定で適合性の悪い関節といわれています。この不安定な関節を安定させるために、靱帯や半月板が膝関節では重要な役割を担っています。 本講義では膝関節の持つ解剖学的な特徴や股関節および足関節の架け橋となるべく運動学についてもお話しさせていただきます。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 股関節 | 岡本 | 2 | ・第12章 股関節 |
| 要約 | 股関節は、人の立位姿勢や歩行場面において安定性に適した解剖学的な特徴を有しています。加えて上半身と下半身との中心的位置にあるため動作時に主要な運動学的役割を担っています。 本講義では骨・筋肉・靭帯・関節だけにとどまらず脊柱との解剖学的・運動学的な関係性についてもお話しさせていただきます。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 股関節 | ・第12章 股関節 |
| 要約 | 股関節は、人の立位姿勢や歩行場面において安定性に適した解剖学的な特徴を有しています。加えて上半身と下半身との中心的位置にあるため動作時に主要な運動学的役割を担っています。 本講義では骨・筋肉・靭帯・関節だけにとどまらず脊柱との解剖学的・運動学的な関係性についてもお話しさせていただきます。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 歩行 | 川上 | 2 | ・第15章 歩行の身体運動学 |
| 要約 | 歩行は日常的に最も使われる移動手段のひとつでそれは下肢だけで行われるのではなく、全身的な”動作”です。そのため、歩行における各関節ごとに焦点を当て解剖学的・運動学的に理解していくことが重要です。 今までに学んだ各関節の知識を用いて我々が普段何気なく行なっている歩行という全身的な”動作” について理解を深め、明日のクライアントの歩き方の見方が変わるようお話しさせていただきます。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 歩行 | ・第15章 歩行の身体運動学 |
| 要約 | 歩行は日常的に最も使われる移動手段のひとつでそれは下肢だけで行われるのではなく、全身的な”動作”です。そのため、歩行における各関節ごとに焦点を当て解剖学的・運動学的に理解していくことが重要です。 今までに学んだ各関節の知識を用いて我々が普段何気なく行なっている歩行という全身的な”動作” について理解を深め、明日のクライアントの歩き方の見方が変わるようお話しさせていただきます。 |
| 単元名 | 講師 | 単元数 |
項目 |
|---|---|---|---|
| 走行 | 川上 | 2 | ・第16章 走行の身体運動学 |
| 要約 | ”待ち合わせに間に合わない”、”急な用事ができて急いでいる”そんな時は少しでも目的地に早く着こうとして”走る”こともあるのではないでしょうか?走行というのは第15章で学んだ「歩行」の単なる延長ではなく走行独自の運動学が存在します。 全身の動きを踏まえて解剖学的・運動学的な視点からお話しさせていただきます。 |
||
| 単元名 | 項目 |
|---|---|
| 走行 | ・第16章 走行の身体運動学 |
| 要約 | ”待ち合わせに間に合わない”、”急な用事ができて急いでいる”そんな時は少しでも目的地に早く着こうとして”走る”こともあるのではないでしょうか?走行というのは第15章で学んだ「歩行」の単なる延長ではなく走行独自の運動学が存在します。 全身の動きを踏まえて解剖学的・運動学的な視点からお話しさせていただきます。 |
講師紹介
岡本 浩明(おかもと ひろあき)
医療法人啓明会相原病院 主任理学療法士
箕面市理学療法士会会長
肩関節・腰・膝関節・股関節の疾患患者、膝関節・股関節の人工関節置換術後患者、膝関節のスポーツ障害に対する術後患者を主とする病院で理学療法士として従事している。
一方で理学療法団体の理事やボディワーカーを対象とした基礎医学セミナーの講師も行っており、臨床以外の場でも活動している。
ヒトの身体をより深く理解するため、より良く導くために学会発表を積極的に行い、知識と技術の向上に奔走している。
川上 純平(かわかみ じゅんぺい)
特定医療法人誠仁会 大久保病院 理学療法士
中枢神経疾患(脳卒中・神経変性疾患)や整形疾患などの患者様に対し幅広く理学療法を展開している。
そのなかで、理学療法からの観点に加え「ヒトの動き」に着目し神経系・環境を重要視したアプローチを実践している。
また、発症・受傷から間もない方や長期の経過を辿る方など様々な時期の患者様へアプローチする中で、身体は常に変化する可能性を持っていることを痛感する。
そしてその変化をより良い方向へ導けるよう「自分(患者様)の身体と常に向き合う」をテーマに活動している。
柳 永善(りゅう よんそん)
みらい鍼灸整骨院院長
柔道整復師・鍼灸師
分子整合栄養アドバイザー
登録販売員
JSC(日本カイロプラクティック師協会)副会長
大阪府生涯スポーツコーディネーター
一般社団法人 動的安定協会 理事
「精神・構造・栄養へのアプローチを行いクライアントの自然治癒力を高める!」
というコンセプトのもと治療を行う。その為の知識・治療技術習得に多くの時間を費やす。
スポーツ選手・不妊症で悩む女性・産前産後の母親への栄養サポートを行い、栄養分野において複数の団体で講師活動も行う。
(五十音順)
講師より追伸:本コースを開講するにあたって


昨今、医療費に分配される予算は削減の一途を辿り、予防医療の重要性が謳われている中、身体に携わる様々な施設・業種・職種が各々の現場で奮闘していると思います。
その一方、患者・クライアントのために治療者・ボディワーカーが手を組めているのか?この点については、甚だ疑問であります。
私が数年前に受講した、ある海外スポーツトレーナーのセミナーの中で、彼は「これは理学療法士に教えてもらったんだけど…」「これはピラティストレーナーに教えてもらったんだけど…」などと、様々な職種との連携を想像するに易い話しが多くありました。
これこそ今日本が望んでいる予防医療〜健康増進〜健康寿命延伸に求められるモノではないか?と考えています。
しかし、資格の枠を超え様々な職種が連携するには、各々の間に共通言語があり、適切に患者・クライアントの状態を伝えられることが重要であると思います。
その際に絶対的に必要になる知識…それが『解剖学・運動学・生理学』といった基礎医学であることは明白です。
さあ皆さん、共に学び、手を取り合って歩みましょう!!
B-college身体の基礎知識ベーシックコース Program Director 岡本浩明
お申し込みは、ホームページから承っております
講座のお申し込みは、左側のボタンをクリックし、フォームに必要事項をご記入のうえお申し込みください。
リテイク(再受講)のお申し込みは、右側のボタンをクリックし、フォームに必要事項をご記入のうえお申し込みください。